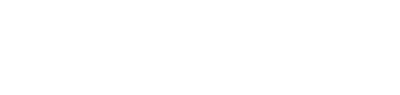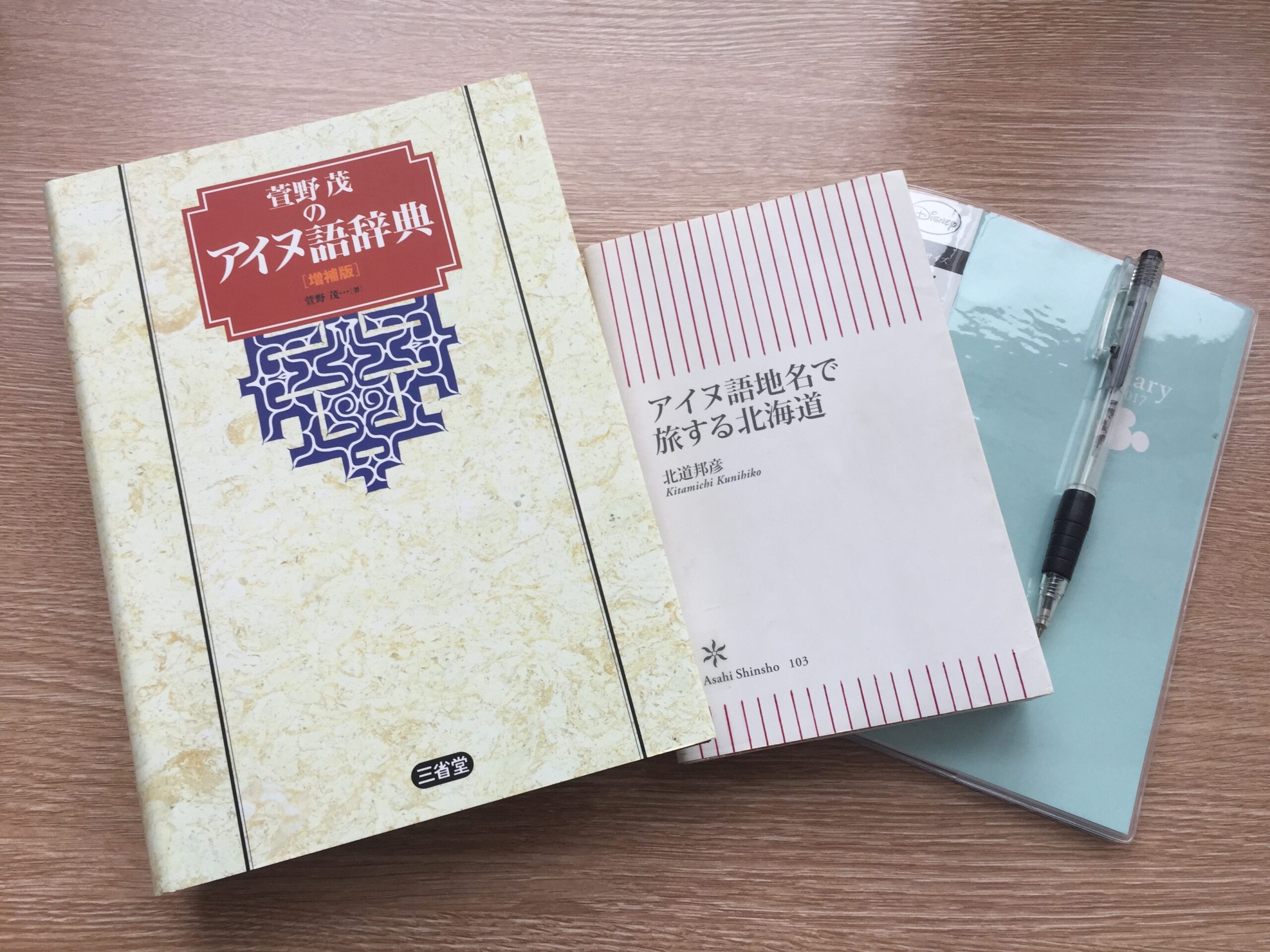当店の屋号【ニセコウッカ】のウッカは日本語で瀬(浅い流れ、流れの早いところ)を意味するアイヌ語です。北海道にはアイヌ語由来の地名、山の名、川の名が沢山ありますが、ニセコにまつわるアイヌ語について、少しだけ調べてみました。ちなみに、【アイヌ】は(人間)を意味するアイヌ語です。
ニセコ
町名であるのと同時に近隣の町村を含めたエリアの呼称でもある【ニセコ】は、ニセコアンベツ川 ニセイ(断崖)コ(に対して)アン(ある)ペッ(川)がその由来となっています。現在では、世界でも屈指のスキーフィールドとして有名なニセコアンヌプリですが、アイヌの人々は山よりも川を重んじたようで、ニセコアンベツの水源があるヌプリ(山)ということで、そう呼ばれていたようです。
倶知安
ニセコウッカのベースがある倶知安町の由来は、実ははっきりしていません。町内を流れる川、倶登山川 クト(崖)サン(から流れ出る)がそのまま由来となっているというのが有力な説のようです。
羊蹄山
ニセコアンヌプリ同様、羊蹄山も真狩川 マッ(後ろ)カリ(をまわる)ペッ(川)の水源があるヌプリ(山)ということで、アイヌの人々は羊蹄山をマッカリヌプリと呼んでいました。近くにそびえる尻別岳との対象で羊蹄山を雌山 マチ(女)ネ(のような)シリ(ヤマ)雌山、尻別岳を雄山 ピン(男)ネ(のような)シリ(山)とうかがったことがあり、なぜ高い方が女のようなのかと疑問を抱いたものですが、どうやら、姿の良い方を女のようなと表現したようです。その後、日本書紀の記述に基づき後方羊蹄(しりべし)と名付けられたものの、読み方が難解なため、羊蹄山に変更されました。標高1898mは北海道で21番目、蝦夷富士と呼ばれてはいるものの、特別高いというわけでもないのですね。活動度の低いランクCの活火山です。ちなみに、現在、休火山や死火山という言葉は廃止され、過去1万年の間に火山活動のあった火山は全て活火山とされ、過去の活動度に応じA〜Cにランク分けされています。
尻別川
ニセコラフティングツアーのフィールドとなる尻別川。【シリベツ】とは、内陸深くからくる川の意で、本来は シリ(山)ペッ(川)と発音します。アイヌの人々が、山の川、と呼んだ尻別川は、千歳市と伊達市との境にあるフレ岳に源を発し、喜茂別町、京極町、倶知安町、ニセコ町と、羊蹄山を廻るように流れ、蘭越町で日本海に注ぐ全長126kmの一級河川です。